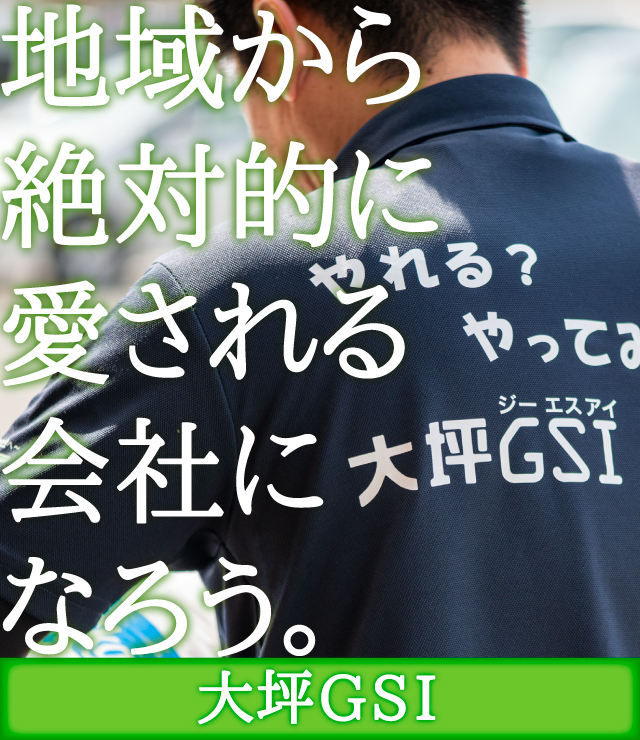SDGsなプロジェクト
九州の企業が取り組むSDGsプロジェクト
SDGsは許可制ではなく自分で手を挙げてやる自律制。 地域から絶対的に愛される会社になろう。
大坪GSI株式会社
大坪GSI株式会社 本社
住所 : 福岡県柳川市大和町徳益416
TEL : 0944-74-6811
https://www.ogsic.jp
社名“GSI”に込められた想い
福岡県内の産業廃棄物処理業者は約420社 (公益法人福岡県産業資源循環協会の会員数) を数え、サービス (商品) での差別化が難しく競争も激しい業界と言える。その厳しい外部環境の中で、SDGsを経営戦略に実装し、社員の意識改革と競合との差別化、そして事業領域の拡大に成功している企業がある。
 大坪GSI株式会社 本社
大坪GSI株式会社 本社
柳川市に本社を置く大坪GSI株式会社。1966年に大坪商店として創業。ダンプトラックによる土木資材の運搬に始まり、砕石の製造販売、工事現場から排出される産業廃棄物のリサイクルへと事業領域を拡大し、2011年には「大坪GSI株式会社」に社名を変更し企業ビジョンを明確に打ち出した。 GSIのGはグリーン (環境) 、 Sはシルバー (高齢化) 、Iはアイデアル (理想的な) を意味し、環境と少子高齢化をキーワードに、理想的な社会の構築に貢献できる会社であり続けたいという思いが込められている。特筆すべきは、この社名変更がSDGsが国連で採択される2015年以前に為されたにもかかわらず、SDGsの特色の一つである、経済・社会・環境の3要素を含める「統合性」がすでに盛り込まれている点にある。
国家プロジェクトから自分事へ
創業者の息子で3代目となる大坪尚宏社長は「SDGsを初めて知ったのは2016年の終わり頃です。2017年には福岡市内で開催されたSDGsのセミナーに出席していますね」と、SDGsとの出会いを振り返る。「SDGsの趣旨にはすごく賛同できるし、語られていることは真っ当なことだと理解はできるものの、ウチみたいな地方の中小企業のビジネスにどうつながるのか? そこがまったくピンとこない。国家プロジェクトとか大手企業の一部の方たちのものだ…というのがSDGsの第一印象でした」。
 大坪GSI株式会社 代表取締役社長 大坪尚宏さん
大坪GSI株式会社 代表取締役社長 大坪尚宏さん
とはいえ、やはり気になるキーワードだったようで、SDGs関連の書籍を読みあさり、SDGsセミナーにも積極的に参加し知見を深めると「環境に携わる事業者である以上、SDGsには必ず関わっておくべきだ」という直感めいた感覚が生まれたという。「産業廃棄物のリサイクル業は、筑後エリアだけでも100社以上あって、差別化できないから価格破壊が起き始めています。今からの時代、どこで差別化するのか? 生き残る術は? と考えた時に、柳川の小さな中小企業が、地球規模の課題であるSDGsに真剣に取り組んでいることで、お客さまから選んでもらえるのではないか? と考えたんです」。
では、どうやったらできるのか。いろいろな資料を読み込んで調べた結果「SDGsは“自分たちもやります”と手を挙げることがすべてでした」と大坪社長は言う。「SDGsは、何か試験があるわけでもなく、許可制でもなく、自分自身で“やる”と決めて宣言するもの。でも、自分で宣言したからには責任を持って“やり続ける”ことが必要で、とても自律的なものだと感じています」。このSDGsの自律性は、大坪GSIのその後の社内改革に良い影響を与えていく。
地域から絶対的に愛される会社になろう!
「産業廃棄物のリサイクル業なので、すぐに3つのゴールには該当しました」という大坪社長。12:つくる責任 つかう責任、13:気候変動に具体的な対策を、そして17:パートナーシップで目標を達成しよう の3つがそれだ。「それで、他にはないか? できることはないか? とみんなで考え始めたんです」とサラリと口にするが、これが、ある意味、大坪GSIの文化ともいえる。
「自分で手を挙げたので責任を持ってやり続けなければ意味がない。いくつかのゴールを自分たちの事業にマーキングして終わりではない。そこで終われば“大坪は言っただけでやってないじゃないか”となる。…となれば、他のゴールでもできることはないだろうか? 地域貢献で何かできないか? と考えたのです」。
-
 SDGs私募債発行にともないNCBから贈呈されたSDGs認定書
SDGs私募債発行にともないNCBから贈呈されたSDGs認定書 -
 同じく福岡県フードバンク協議会から贈呈された感謝状
同じく福岡県フードバンク協議会から贈呈された感謝状
柳川高校との協働から始まった地域貢献
大坪GSIの地域貢献は、地元・柳川高校とのコラボレーションを模索するところから始まる。「柳川高校には商業高校のDNAがあり、商業科では実践的なビジネスを学んでいます。大学と企業のコラボはよく聞くけれども、高校と中小企業のコラボはあまりない。僕自身の母校でもあるし、なんとかできないだろうか? という思いでした」と大坪社長は振り返る。「うまく、古賀校長先生とアポイントが取れて、商業科の生徒に向けて、地元の企業と一緒に机上ではなく“生きた授業”をしませんか? とお話をするとすごく乗っていただいて、ご一緒することができました」。
入社2年目となる大坪GSI 企画営業課の田中将弘さんと伊香賀彩さん。若手2人が柳川高校商業科と一緒に取り組んでいるのが「クラウドファンディングの返礼品を地元企業とコラボして企画開発する」というもの。柳川高校では、生徒たちが部活動の一環で、地域活性化のために新しい特産品を商品化するという企画でビジネスプラン・コンテストに出場。惜しくも受賞を逃すも、なんとか商品化すべく、試作品の制作費をクラウドファンディングで調達し商談会への出店を果たしている。その商品とは、柳川で出た廃材のシートベルトなどを素材に、有明海に生息するワラスボをモチーフにデザインした「ワラスボリュック」だ。商品の素材もモチーフも加工も“オール柳川”なので、クラウドファンディングの返礼品も、やはり地元コラボで数種類を開発しているという、まさに“生きた授業”である。「クラウドファンディングの返礼品の一つで、弊社の『リグラスチップ』という、廃材ガラスを再加工した装飾用のガラスカレットを使って、手作りのフォトスタンドを企画しました。開発会議に出席した際に、他の返礼品で、やはり柳川の企業さんのコラボで神棚の木材を使ったストラップを開発されているのが印象的でした」という伊香賀さん。「おかげで地元・柳川の魅力を知ることができて、新しい人との繋がりも生まれました」とは田中さん。高校生と年齢が近いということもあるが、あえて若手2人をこの取組みの担当に据えた大坪社長の狙いが見えてくる。
-
 柳川高校でのミーティングの模様(大坪GSIのHPより抜粋)
柳川高校でのミーティングの模様(大坪GSIのHPより抜粋) -
 大坪GSIの「リグラスチップ」(大坪GSIのHPより抜粋)
大坪GSIの「リグラスチップ」(大坪GSIのHPより抜粋)
“五方よし”の精神
SDGsの解説でもよく登場する、SDGsは“近江商人の三方よし”の考え方のようなものという話。“自分よし、相手よし、世間よし”の精神だが、大坪社長は“五方よし”を唱えている。「社員よし、お客さまよし、仕入れ先よし、取引先よし、地域社会よしの“五方よし”の精神は、常に社員に説いています。私たちは、地域からも取引先からも絶対的に愛される会社になろう! この街には大坪GSIが絶対に必要だ! そう言ってもらえるようでなきゃならない。そうなれば (ウチは) 絶対に潰れない。なぜなら、ウチが困ったときは周りの人が助けてくれるから…と。そして、もしそんな存在になりたければ、自分が求めるだけじゃダメ。地域やお取引先で困っている方があれば、自分で現場に行って、お困りごとを解決するためにできる限りのことをしなきゃならない」。
これが、2011年に大坪GSI株式会社に社名変更した際に掲げた大坪GSIの使命、つまり「世の為、人の為、地域のために何ができるかを希求する」の本質である。その精神が、SDGs達成の取組みを通じた事業領域の拡大へと導いていく。その典型的な事例が糸島の「シーライム」事業といえる。
糸島の牡蠣殻を農地に還す
糸島の冬の風物詩ともいえるカキ小屋は、1シーズンで約40~50万人もの利用客が訪れる地域の貴重な産業資源のひとつ。意外にもその歴史は浅く、糸島で牡蠣養殖が始まったのは1990年頃で、2000年代に入ってから本格的に事業規模が拡大していく。しかも、生産量の80%以上が生産地に立地するカキ小屋で消費され、市場に出回るのは数%という特徴を持つ。産業の急成長とともに問題となったのが牡蠣殻の処理。カキ小屋から排出される焼きカキの殻と、養殖時に十分成長できなかったへい死貝の殻の処理は、せっかく地場産業として定着してきた牡蠣養殖にとっては喫緊の課題となっていた。
その課題を解決したのが、2010年に発売されたJA糸島のオリジナルカキ殻石灰「シーライム」だ。カキ小屋から排出される牡蠣殻を粉砕加工し、土を肥やす有機質石灰として商品化するというスキームは、海の恵みを土に還し、その肥沃な土が豊かな川の流れを通じて海に流れ込み、再び豊かな糸島の海を育むという地域の資源循環のモデルケースとして注目を集め、もちろん糸島生まれの安心安全な良質石灰として人気の商品となった。
-
 JA糸島のオリジナルカキ殻石灰「シーライム」
JA糸島のオリジナルカキ殻石灰「シーライム」 -
 「シーライム」を専売するJA糸島アグリ
「シーライム」を専売するJA糸島アグリ
このシーライム事業の生みの親が、JA糸島 経済部の古藤俊二さん。「カキ小屋の牡蠣殻は、最初は全部可燃ゴミ扱いで、割り箸やら紙パックやらと一緒にまとめて廃棄されていました。処理費も高額で集荷も重くて大変で。そこで行政が音頭を取ってリサイクルの話 (シーライム事業) が立ち上がります。まずは牡蠣殻の分別が大変で、カキ小屋を1軒づつ回って分別のお願いをするところからでした。最初は、まだまだご理解をいただけなかったのを (糸島) 漁協さんがまとめてくれて。全部のカキ小屋に青いバケツと黄色いバケツを用意してくれて、青には牡蠣殻だけを入れようって。カキ小屋のお客さんにも協力をお願いしてくれて。それでずいぶんとシーライムの事業が進められるようになりました」と当時を振り返る。
 JA糸島 経済部 部長補佐 古藤俊二さん
JA糸島 経済部 部長補佐 古藤俊二さん
窮地を救った「何かできるかも」という電話
農協・漁協・行政、加えてカキ小屋を利用する市民の協働で生まれたシーライムは、しかし2016年、粉砕処理を委託していた処理業者の廃業により頓挫する。加工ができなくなり商品の供給がストップ。シーライムは市場から消えた。
「本当に困りました。いっそ自分たちで加工しようかとも考えましたが、用地の確保もできませんし、新たに機械を購入する費用もなく。でも牡蠣殻は排出され続けている。せっかく地域の資源循環モデルとして確立できたものを無駄にしたくないし。ちょっと打つ手がなかった」と古藤さん。
解決策が見出せぬまま、1年半が過ぎようとしていた2018年の夏、古藤さんの元に一本の電話が入る。業界誌の記事で糸島の窮地を知った大坪社長(当時は専務)から「ウチで何かお手伝いできるかもしれません。一度会っていただけますか? 」と。困っている地域や人を何か助けることはできないか? まさに大坪GSIの真骨頂だ。「びっくりしました。面識もないし、まして柳川の会社さんですから。それでも、何度も(糸島に)足を運んでいただいて、電話で済むような話も直接会いにきてくれて。シーライム対する愛情を感じて、本当に感謝しています」と古藤さんは言う。
 大坪GSI 企画営業課 課長 椛島浩幸さん
大坪GSI 企画営業課 課長 椛島浩幸さん
ついに、2018年春、シーライムは復活し再販売が始まる。とはいえ決して簡単な事業再開ではなかった。シーライム事業を担当する大坪GSI 企画営業課 椛島浩幸課長は「手を挙げたのはいいけれども、事業として利益を確保するのが難しいチャレンジでした」と言う。「まず、シーライムの販売価格が安いんです (20kg 520円) 。でも商品の性質上、値上げができないので、古藤さんからは“ぶっちゃけ○○円で入れてくれないとお願いできません”と最初に明確に提示されました。それが逆に良かった部分もあって、はっきりとターゲットが見えました。幸いウチが持ってる機械を組み合わせて調整することで対応できたので、新たな設備投資も不要でしたし、技術的にも問題ない。一番は輸送コストでした。なので、柳川からシーライムを積んで納品した後に、空の荷台に牡蠣殻を積んで柳川に帰るというルールは絶対です。納品と集荷をバラバラにやると赤字ですね」と笑う。
糸島漁協をまとめた伝説の参事
シーライムの復活に欠かせない登場人物がもう一人。荒ぶる海の男たちをひとつに束ねた、糸島漁協の吉村寿敏参事だ。「糸島の牡蠣は歴史が浅いんです。カキ小屋にたくさんの人が来ていただけるようになったのも最近で、牡蠣殻が急激に増えてきて、それをなんとかしないといけないという課題があったので、そこが古藤さんと一緒だったんです。元々、糸島の牡蠣は脊振山系の山の恵みが川を通じて海(牡蠣)を育てているという仕組みなので、漁協でも、脊振の山の植樹活動なんかも毎年30~40人出してボランティアでやっていました。シーライムも、海の栄養を山に戻そうという資源循環型の商品なので、それで“一緒にやろうか”ってなったわけです」。
 糸島漁業協働組合 参事 吉村寿敏さん
糸島漁業協働組合 参事 吉村寿敏さん
先に紹介したカキ小屋で牡蠣殻の分別を開始したことも大きな意味を持つが、シーライムの再販売にあたっては、漁協主導でリサイクル専用の牡蠣殻のストックヤードを造ったことが大きな意味を持つ。「漁協の牡蠣部会には約30の漁業者が所属していて、これまでは6つの漁港でそれぞれに牡蠣殻をストックしていましたが、今回、専用のヤードを造って1つにまとめました。それぞれの事情はあるだろうけれども、皆さんに協力をいただいています」と語る吉村参事。先に紹介したとおり、シーライム事業は輸送コストがボトルネックで、仮に牡蠣殻の集積場が複数箇所に分散していたら、大きな事業課題になっていたに違いない。シーライム事業には、糸島の地域産業を糸島らしい手法で守りたい、その志の元に、何か目に見えない力で、必要な登場人物が集められているようにすら感じる。
-
 「シーライム」専用の牡蠣殻のストックヤード
「シーライム」専用の牡蠣殻のストックヤード -
 脊振山系の恵みが詰まった糸島の牡蠣
脊振山系の恵みが詰まった糸島の牡蠣
 糸島漁協の事務所がある岐志漁港。店舗型にリニューアルしたカキ小屋が軒を連ねている。
糸島漁協の事務所がある岐志漁港。店舗型にリニューアルしたカキ小屋が軒を連ねている。
そして、社員が変わった。
「SDGsに真剣に取り組むことで、自分たちがやっていることの意味がはっきりした部分があると思います」と大坪社長は言う。先にも触れたが、SDGsが国連で採択される以前に、大坪GSIは社名変更にあたり「世の為、人の為、地域のために何ができるかを希求する」ことを使命と定めている。「これまで社員それぞれが“私がやります”と手を挙げて取り組んできたことの意義が、SDGsのおかげで明確化されると、次に何か新しいことに取り組もうとするモチベーションになります。(ウチでは) どんなことでも“私がやります”と手を挙げると (手を挙げた) あなたが主人公です…と説いています。社歴や年齢は関係ありません。周りの社員は (手を挙げた人を) サポートします。この感覚は「誰一人取り残さない (leave no one behind) 」と宣言したSDGsと通じるものがありますね」と語る社長の頭の中には、もう次の新しいプロジェクトが動き出しているように見えた。